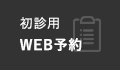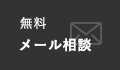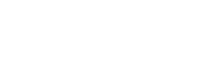豆知識
抜歯後インプラントはいつできる?適切なタイミングと放置した場合の対処法
▼目次
1. インプラントは抜歯してからどのくらいで治療できる?
2. 抜歯後にインプラント埋入をすぐにできるケース・待つべきケース
3. 抜歯後何年も放置してしまった時の注意点と対処法
4. 京都二条たけち歯科クリニックのインプラント治療について
抜歯後、インプラントはいつ入れられるのか気になる方も多いのではないでしょうか?すぐに治療できるケースもあれば、骨や歯肉の状態によって待つ必要がある場合もあります。さらに、歯がない状態で長期間放置すると骨が痩せてしまい、追加の処置が必要になることもあります。今回は、抜歯後のインプラント埋入の適切なタイミングと、放置してしまった場合の対処法について詳しく解説いたします。
1. インプラントは抜歯してからどのくらいで治療できる?
インプラント治療は、失った歯の機能と見た目を取り戻すための方法として多くの人に選ばれています。ただし、抜歯後にすぐにインプラントができるとは限りません。治療開始のタイミングは、骨の状態や炎症の有無など、さまざまな要因に左右されます。以下に、抜歯後のインプラント埋入のタイミングについて解説いたします。
①即時埋入(そくじまいにゅう)
抜歯した直後、傷口が新鮮なうちにインプラントを埋め込む方法です。傷の治癒を待たずに行うため、通院回数や治療期間を短縮できる場合があります。ただし、歯周病が進行している場合や、骨の状態が不十分な場合は適応外となることがあります。
②待時埋入(たいじまいにゅう)
抜歯から4か月以上経過し、骨や歯肉がしっかり治癒した状態でインプラントを埋入する方法です。最も確実性が高く、リスクが比較的少ないとされていますが、治療開始まで時間がかかることがデメリットです。 上記以外にも、患者様の健康状態や全身疾患の有無、生活スタイルに応じて治療スケジュールが調整されることもあります。歯科医師の判断のもと、無理のない計画が立てられます。
2. 抜歯後にインプラント埋入をすぐにできるケース・待つべきケース
インプラント治療の開始時期は、誰でも同じではありません。口腔内の状態や原因となった疾患の進行具合によって、適切なタイミングは異なります。 以下に、抜歯後にインプラント埋入がすぐにできるケースと、待った方がいいケースについて解説いたします。
<すぐにできるケース>
・歯周病や炎症がなく、骨の状態が良好 ・外傷による抜歯で、周囲の組織にダメージが少ない ・歯肉の形が整っていて、追加処置の必要がない このような場合は、抜歯直後にインプラントを行う「即時埋入」が検討されることがあります。
<待った方が良いケース>
・重度の歯周病で骨が溶けている ・むし歯の進行で周囲の組織に炎症がある ・抜歯部位に膿が溜まっている、または傷の治りが遅い これらのケースでは、炎症を抑えてからでないと、感染リスクが高くなる可能性があります。 また、以下のような場合には注意が必要です。
①骨の量が不足している場合
抜歯後に骨の量が少ないと、インプラントを支える土台が不安定になりやすいです。このような場合は、骨を再生する「骨造成(こつぞうせい)」という処置が必要になることがあります。
②糖尿病や喫煙習慣がある方
これらの要因は、傷の治りを遅らせるだけでなく、インプラントの安定性にも影響を与えることがあるため、慎重な経過観察が求められます。
③噛み合わせに問題がある場合
インプラントを入れても、その上にかかる噛む力が偏っていると、脱落や破損のリスクが高まります。こうした場合は、矯正や噛み合わせの調整を先に行うこともあります。 インプラント治療の成功を左右するのは「タイミング」と「土台の準備」です。まずは歯科医師としっかり相談し、自分にとって最適な治療開始時期を見極めましょう。
3. 抜歯後何年も放置してしまった時の注意点と対処法
歯を失ってから何年もそのまま放置しておくと、噛み合わせのバランスが崩れたり、見た目に影響が出たりすることがあります。実は、長期間放置するとインプラント治療の難易度が上がる傾向がありますが、適切な処置を受ければ、治療が可能な場合もあります。以下に、抜歯後何年も放置してしまった時の注意点と対処法を解説いたします。
<注意点>
①骨が痩せてしまっている可能性がある
歯を失った部分は、噛む刺激が伝わらなくなることで、顎の骨が徐々に痩せていく「骨吸収」が起こります。骨が極端に少ないと、インプラントをしっかり支えることが難しくなるため、まずは骨の状態を確認する必要があります。
②周囲の歯への影響も考慮する
長期間放置すると、周囲の歯が空いたスペースに倒れてきたり、噛み合わせが乱れたりすることがあります。これらがある場合は、インプラント治療前に矯正や噛み合わせの調整が必要になることもあります。
<対処法>
①まずは精密検査からスタート
放置期間が長い場合でも、まずは歯科医院での精密検査を受けることで、現在の状態を把握することができます。CT撮影や噛み合わせのチェックなどを通じて、適切な治療計画が立てられます。
②骨造成で土台を再構築
骨吸収が進んでいても、「骨造成」という処置でインプラントの土台を作れる可能性があります。これは、人工的に骨を補填したり、再生を促す薬剤を用いる治療法です。数ヶ月の準備期間が必要ですが、将来的なインプラントの安定性にとって重要な工程です。
③生活習慣の見直し
喫煙、歯ぎしり、糖尿病などがあると治療に影響を及ぼす可能性があります。治療を始める前に、生活習慣を見直し、全身の健康を整えることが、成功率を高めるポイントです。 長期間放置してしまった場合でも、諦める必要はありません。インプラント治療は進化しており、多くの選択肢が用意されています。まずは現状を知るところから一歩を踏み出しましょう。
4.京都二条たけち歯科クリニックのインプラント治療について
インプラントのデメリットの一つに「手術が必要」ということがあります。 この「手術の恐怖」と、「それを乗り越えた時のこの上ない素晴らしい快適さ」。 この間にある大きな溝を埋めることが京都二条たけち歯科クリニックの使命だと考えています。 当院では患者さんに合わせた様々な治療法があります。
<手術に恐怖心を持っておられる方におすすめのインプラント治療法>
・メスで切らないインプラント(フラップレス手術)
メスを使わず、歯肉をめくったり、縫ったりしない治療法です。 手術時間が短時間で済み、術中の痛みが少なく、終わった後の痛みや腫れを抑えられるのが特徴です。
・静脈内鎮静法によるインプラント
静脈内鎮静法での手術ならウトウトとしている間に手術が終わってしまいます。 全身麻酔は意識がなくなりますが、静脈内鎮静法では意識はありますがうたた寝をしているような、とてもリラックスした状態で手術を受けることができます。
<総入れ歯でお困りの方におすすめの治療法>
・人工歯をシッカリ支えられるAll-on-4(オール・オン・フォー)
費用面や手術自体の負担を大きく軽減した治療法で、全ての歯を失った方(無歯顎)対象のインプラント方法です。 4本のインプラントを支えにしてかぶせ物を12本作ります。(5~6本のインプラントを使う場合もあります。) 人工歯はインプラントによって顎の骨とつながっていますので、従来の歯肉との吸着力で支える入れ歯とは異なり、生来の歯と同じように力を入れて食べ物を噛むことができます。
まとめ
抜歯後のインプラント治療は、タイミングや口腔内の状態によって最適な方法が変わります。すぐに治療できる場合もあれば、準備期間を必要とする場合もあり、抜歯後の放置期間が長くても骨造成などの対策で治療が可能になるケースもあります。まずは歯科医師と相談し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。 京都二条たけち歯科クリニックでは、患者様一人ひとりに適したインプラント治療を提案しております。 京都府 京都市でインプラントを検討している方は、京都二条たけち歯科クリニックまでご相談ください。
監修:武知 幸久
経歴:
1989年 徳島大学歯学部卒業
1997年 たけち歯科医院開業
2011年 医療法人社団翔志会
たけち歯科クリニック開設
京都市立病院 登録医